心リハ指導士の勉強をしていくうえでいちばんやりにくいというか、やる気が出にくい原因になるのが、「過去問がない」ということです。
心リハ学会の会員であれば(当然受験予定の方は入会しているはずなんですが)、一部は学会のページでログイン→「心臓リハビリテーション指導士試験」などのキーワードで書誌情報検索すると入手できます。
・・・入手できるんですが、ごくわずか。しかもなんだか難しめの問題ばかりで余計に不安をあおられます(笑)
どんなジャンルの勉強でもそうですが、知識の詰め込みだけでは集中が続きません。最後にテストがあって、「あ、この分野はやったつもりで全然頭に入ってなかったな」とフィードバックがあって復習して・・・というループの中で初めて知識って定着していくんですよね。
Contents
心リハクイズ作ってみました
ということで、クイズを作成してみました。予想問題ではありません、クイズです。この先はそういうニュアンスを理解できる方だけ読み進んでください(笑)
私が個人的に勉強した文献、参考図書をもとに問題を作成しておりますので、可能な範囲で内容を吟味はしていますが、その正確性を保証するものではありませんのでご了承ください。
なお、解説を全力でつけると作業時間が大幅に増えてしまうので(笑)、解説は最小限にしてあります。知識があやふやだった部分は参考書にあたるなどして復習していって下さい。
第1問
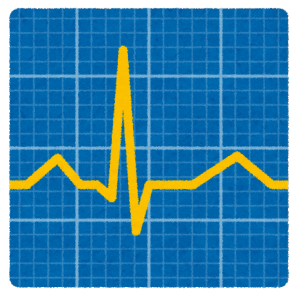
解答
正解:1.4
1.右室梗塞の評価に有用です。
2.四肢誘導はそのままです。電極位置はV3-V6で左右対称になります。
3.後壁梗塞疑いの場合、背部誘導(V7-V9)で異常Q波やST上昇の所見を確認します。
広範前壁梗塞ではⅠ、aVL、V1-V6で心電図変化があることが多いとされます。
4.V1-V2の電極位置は変わりません。
5.導出18誘導心電図は12誘導心電図の波形をもとに、右側誘導(V3R・V4R・V5R)、背部誘導(V7・V8・V9)の波形を演算処理して導出したもので、計測自体は通常の12誘導と同じです。
まとめ
心電図はいろいろな形で必ず試験に出ると思われますので、事前の学習は必須です。正常波形、危険な不整脈、どの部位の梗塞でどの心電図が変化するか、など基本的なところはしっかりおさえておく必要があります。
加えて、今日の問題のように右側胸部誘導や背部誘導に関しても、何を目的としてその心電図をとるのか、という点は理解しておくことが重要です。
本当はこのエントリーで3問作る予定だったのですが・・・1問作るだけでけっこうな時間がかかってしまいました(笑)
うまく時間を見つけてさらに問題を作っていこうと思いますので、ぜひ試験勉強の参考にしてみてください!
